第16回年賀状思い出大賞
㈱グリーティングワークス(徳丸博之代表取締役会長)が企画し、日本郵便が後援する「第16回年賀状思い出大賞」で各賞に輝いた感動の受賞作から、佳作5~8を紹介する。
佳作5 赤い林檎 様 「年賀状で支えあう人生」
二十四歳、私の教員人生はスタートした。中学一年生の担当だった。担任ではなかったが、数名の生徒が「先生に年賀状を送りたい」と言ってくれた。その中の一人の女子生徒は、高校三年生まで、毎年年賀状で近況を報告してくれた。生徒のその後の成長を知ることができ、とても嬉しかった。
高校三年生の時の年賀状に「仙台の専門学校に進学します。先生に会いたいです」と書いてあった。毎年年賀状をくれた感謝を伝えたくて、私は年賀状に連絡先を書いて送った。
五年ぶりに再会を果たした。十八歳になった彼女のまっすぐな瞳、可愛らしい笑顔はあの頃と変わらない。その姿に嬉しくなった。

彼女は地元に就職し、今でも定期的に会っている。昨年、成人式を迎えた。若くて力不足だったけれど、想いが届いた気がした。
誰かひとりでも心に残る先生になれたらいい。彼女からの年賀状は、教師を続ける支えにもなっている。
佳作6 友井わさび 様 「続いていく年賀状コンテスト」
「お願いがあるのだけれど、年賀状を送ってくれる? 」義母から年末に連絡がきた。普段はほとんどやり取りをしないのだが、その年は特別だった。待望の子供が生まれたのだ。
義実家は熊本にある。生まれたてのわが子を連れての帰省は見送りになった。そこで年賀状というわけだ。
急遽、年賀状用の撮影会を実施することになり、家の中は活気づいた。どちらが撮った写真がよりかわいいか、どちらのデザインが良いか、夫婦で競い合いながら楽しく年賀状を作成した。結局、二通の年賀状を送ることに決め、初めての年賀状コンテストは終了。翌年以降も、この年賀状コンテストは続いている。
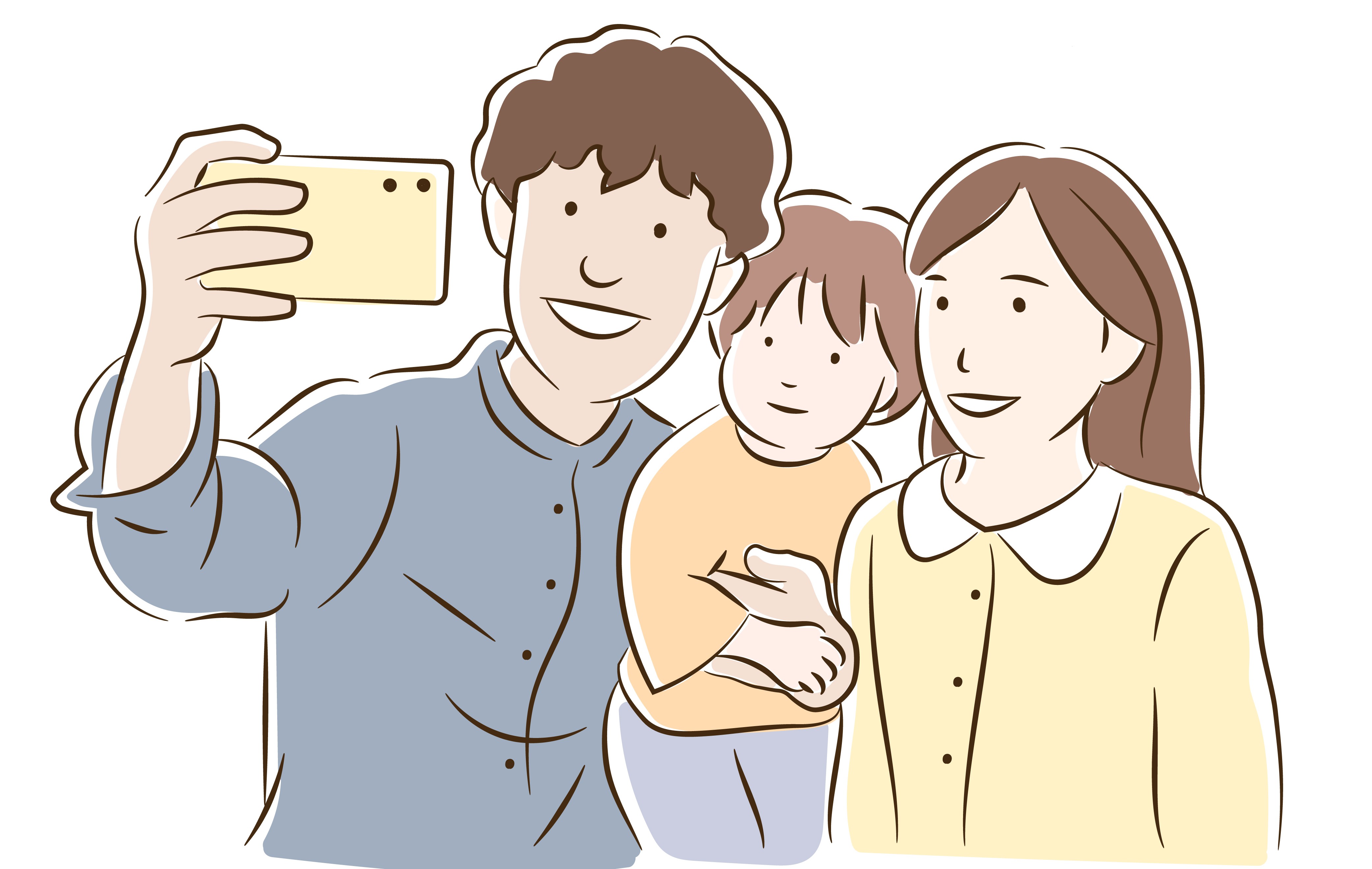
もはや、わたしたちにとって年賀状は単なる年始の挨拶ではない。子の成長を知らせる大切なツールになっている。
歩くようになった子と帰省すると、年賀状が額に飾られている。子がもっと大きくなった時、一緒に年賀状を作るのが今から楽しみで仕方ない。
佳作7 わし 様 「片付け中に見つけた親心」
私は昨年、新社会人として働き始めたが、職場の雰囲気に馴染めず、数ヶ月で鬱病を患い休職することとなった。
自宅療養中、部屋の片付けをしていると、昨年母親からの年賀状を見つけた。それは大学最後の正月にもらった唯一の年賀状であり「身体に気をつけて仕事頑張ってね」と書かれていた。

今までの私は「身体に気をつけて」という言葉に特別な意味を感じることはなかったが、この時は弱っていた心に沁み渡り、自然と涙が溢れ出てきた。年賀状の写真を見ると、実家の様子が懐かしく思えてきて、今まで大切に育ててもらったことへの感謝の思いや、体調を崩してしまったことへの申し訳なさなど、様々な感情が渦巻いた。この年賀状には、母親の愛情や優しさ、温かさが詰まっており、親心を感じることができた。
これからの人生はまだまだ長い。この年賀状を心の頼りにし、健康第一を心に刻んで今後の人生を歩んでいきたい。
佳作8 松葉三代子 様 「かけがえのない友人」
保育園の調理員という仕事で出会って、約三十年の三人。定年を迎えてもパートで働き続ける者、すでに家庭に入った者とそれぞれだ。
旅行も行くし、何ヶ月かに一度はお茶もする。それでも毎年届く年賀状。それはただの新年の挨拶ではない。「今年こそ〇〇へ旅行に行こう」「こんな事を始めてみたい」など、自分たちの目標を掲げたりする。そして普段は口にしないが、改めてそれぞれの存在に感謝する言葉を添える。一年の最初の日にこの年賀状を手にすると「ああ、やっぱりこの二人と友達で良かった」としみじみ思う。

やがて三人も高齢者になり、年賀状が安否確認の手段になってしまうかもしれない。でも、どんなに年老いても「あけましておめでとう。今年もよろしく」という新春の挨拶は、私に元気をくれるだろう。
義理の年賀状はもう辞めた。宛名もパソコンで印刷するようになった。それでも、必ず手書きで深謝の一言を添えて、今年も二人に年賀状を送る。
